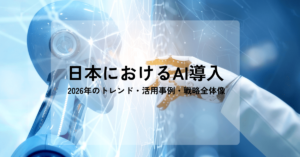ニアショア開発とは?オフショア開発との違いやメリット・デメリットを解説
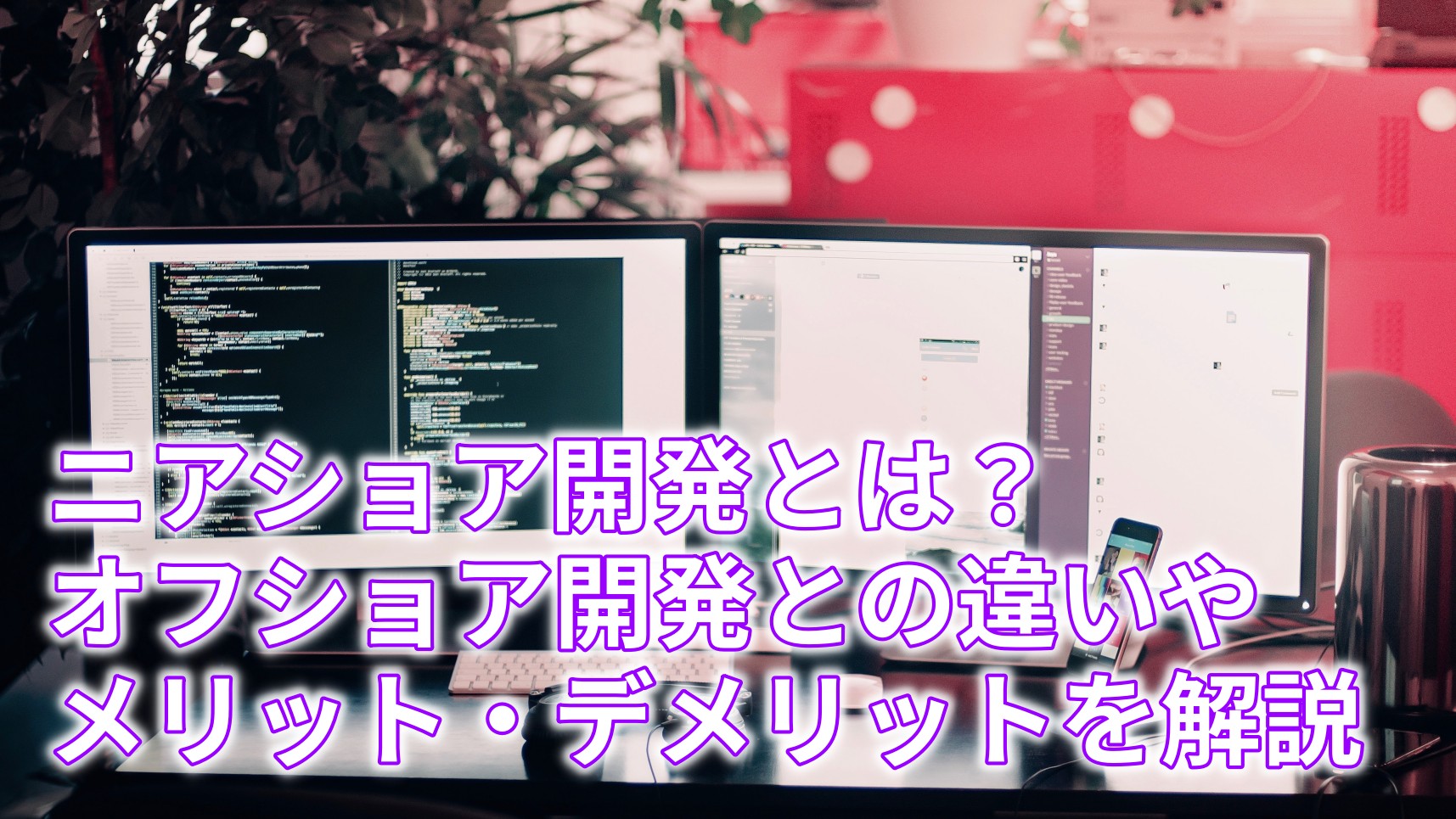
システム開発を外部に委託する企業は多く、さまざまな手法が存在します。
これまでは、中国やインド、ベトナムなど、日本よりも人件費や物価が安い新興国の企業へ発注するオフショア開発がよく知られてきました。
弊社でも、オフショア開発での多くの開発実績があります。
しかし近年は、システム開発をおこなううえで、同じ国内企業に外注する「ニアショア開発」を選択する企業が増加しています。
一見似ているこのふたつの手法ですが、その内容や得られるメリットについては、多くの違いがあります。
そのため、開発を委託するうえで、オフショアとニアショアのどちらを選ぶのかは、非常に重要なポイントとなります。
「オフショアとニアショアの違いって何?」
「ニアショアと普通の受託開発の違いって何?」
そう考えたことがある人も多いのではないでしょうか。
この記事では、地域活性化としても注目されるニアショア開発について、この手法の内容とオフショア開発との違い、メリット・デメリットなどを解説していきます。
合わせて、近年になってニアショア開発が注目される背景と、この手法で開発を進めることが向いている案件についても見ていきましょう。
ニアショア開発とは
ソフトウェア開発の手法として注目されるニアショア開発。
このニアショア開発がどのような手法なのか、オフショア開発との違いや注目される背景、そしてニアショア開発が向いている案件について解説していきます。
国内企業へ外注して開発する
ニアショア開発は、ソフトウェア開発を国内の企業へ外注する手法です。
とくに首都圏にある企業が、地方の企業へ開発案件を発注することを指して「ニアショア開発」と呼びます。
ソフトウェア開発において、保守や運用を外注することは一般的ですが、開発を外部企業に委託することも少なくありません。
ニアショア開発は開発コストの削減をはじめ、リスクの分散や他企業との連携などを目的として採用される手法です。
また、近年は政府の後押しもあり、仕事の少ない地方企業へ案件を発注することで、地方活性化を促進したいという狙いもあります。
オフショア開発との違い
開発を外注する手法としては「オフショア開発」というものもあります。
ニアショア開発とオフショア開発は、どちらもコスト削減や人材確保などを目的として採用されますが、その内容は異なります。
ニアショア開発とオフショア開発の違いは、外注先の企業が、国内にあるか海外にあるかという点です。
詳細に言うなら、オフショアをしている企業には、弊社のように日本法人を持っている企業もあります。
そのため、
「実際に開発するエンジニアが国内にいるか、海外にいるか」
の差と考える方が良いでしょう。
オフショア開発は、国内よりも物価や人件費の安い国へ外注します。
オフショア開発は、大企業を中心に積極的におこなわれていたのですが、近年は中国をはじめ、新興国が経済的な発展を遂げたことで物価・人件費が高騰し、以前ほどコスト面での効果は薄くなりました。
現在はベトナムやインドなどの、IT教育が進んでいる国がオフショア開発の外注先に選ばれることが多いです。
ニアショア開発はオフショア開発と比べると、コスト削減や人材確保といった効果は少ない手法です。
一方で、オフショア開発につきものの、労働習慣やコミュニケーションでの困難がないという利点があります。また、トラブル発生時の対応のしやすさという点でも、ニアショア開発の方が優れていると言えます。
このように、ニアショア開発とオフショア開発には、さまざまな違いがあるのです。
ニアショアと受託開発の違い
これまでの一般的な開発方法などに関しても、
「国内企業に外注する」
という事は多々行われていました。
では、このニアショアと通常の受託開発の違いはあるのでしょうか。
ここには、大きな違いはありません。
ただ、一般的にはニアショアは
「首都圏ではなく、地方のエンジニアへの依頼」
を指す場合が多いです。
例えば、東京にある企業にシステム開発を発注し、その企業は地方にいるエンジニアへコーディングを依頼する。
このような場合にニアショアと言われます。
そのため、通常の受託開発の方法の1つとしてニアショアがあるようなイメージで考えると良いでしょう。
ニアショア開発が注目される背景
ソフトウェア開発を地方企業に外注する手法は以前からおこなわれていましたが、なぜいまニアショア開発が注目されているのでしょうか。
理由としてはまず、国内において、首都圏のみならず地方にまでIT企業が増加したことが挙げられます。
国内のIT企業が少なかった時代は、必然的に海外の企業が外注先として選ばれていました。
しかし現在では地方にも多くのいIT企業があるうえ、海外の人件費が高騰したこともあり、コスト的にも国内企業を選ぶ利点が増えています。
さらに、テレワークの推進や働き方改革の影響もあり、クラウドやツールを用いて遠隔で開発をするという考え方が定着しました。
こうした状況を受けて、多くの企業でニアショア開発が注目され、さまざまな案件が生まれているのです。
ニアショア開発が向いている案件
ここでは、ニアショア開発に向いている案件の特徴を、いくつか解説します。
まず、要件定義をはじめとする上流工程を外注する場合は、ニアショア開発が向いています。
ニアショア開発の強みは、緊密なコミュニケーションが可能なことであるため、高度な議論が求められる上流工程は、国内企業に発注すると良いでしょう。
次に、要求リソースが少ない案件も、ニアショア開発に向いています。
海外に発注するオフショア開発は、規模の大きな案件でないとコスト的に釣り合わないことが多いですが、ニアショア開発であれば、少ない人員で進めたい案件であっても、コスト削減のメリットを得ることができます。
最後に、開発にあまり時間をかけられない案件は、ニアショア開発が合っています。
オフショア開発の場合、トラブル対応や外注先との調整など、時間のかかる工程が多くあります。
そのため、それよりも時間のかからないニアショア開発は、スピーディな開発が可能な手法です。
ニアショア開発のメリット
ここからは、ニアショア開発のメリットとデメリットを解説していきます。
まずは、この手法のメリットを見ていきましょう。
開発コストの削減
開発コストを削減できるというのが、ニアショア開発のメリットのひとつです。
地方の企業は首都圏と比べて賃金が低い傾向にあるため、人件費を抑えることが可能です。
また、外注先の企業が距離的に近いほど人員の移動もしやすく、オフショアと比べて交通費などのコストも大幅に削減できます。
外注をしつつ、より少ないコストでソフトウェア開発を進められるのは、ニアショア開発の利点です。
円滑なコミュニケーションが可能
ニアショア開発は外注先も国内企業であるため、円滑なコミュニケーションが可能です。
オフショアの場合は、言語や習慣の違いという障害があり、外注先の企業とのコミュニケーションには仲介役が必要になります。
これを、専門職として「ブリッジエンジニア」などと呼ぶこともあるくらいに、仲介にはスキルが必要です。
そのため、細かい仕様を伝えたり、話し合いをしたりといった場面で苦労することが多いです。
その点ニアショアにはそうした障害がなく、また距離的にも近いため、コミュニケーションは格段にやりやすいです。
トラブル発生時にも対応がしやすいので、ニアショア開発の大きなメリットと言えます。
災害リスクの低減
複数の開発拠点を持つことで、災害によるリスクを抑えることが可能です。
地震や台風が多発する日本においては、すべての企業が災害によって活動が停止するリスクを背負っています。
ニアショア開発によって、開発を進める場所を分散させることで、災害による企業活動の停止を防ぐことが期待できます。
地域活性化につながる
ニアショア開発はまた、地域活性化につながるというメリットもあります。
首都圏の一極集中が問題となる中、日本政府は地方活性化のため、補助金をはじめとするニアショア優遇の制度を打ち出しています。
首都圏の企業がニアショアを活用することで、こうした制度の恩恵を受けられるだけでなく、地方でも案件が増加し、地域活性化につながります。
地域活性化には人材育成の面もあり、地方でも案件が増加すれば雇用も促進され、優秀な人材が多く育つ土壌ができあがります。
ニアショア開発のデメリット
コスト削減やコミュニケーションの容易さなど、さまざまなメリットがあるニアショア開発。
ですがその一方で、いくつかのデメリットも存在します。
オフショア開発と比べてコストがかかる
首都圏よりも賃金が低い地方の企業に発注することで、国内で開発をしつつもコストを抑えることのできるニアショア開発。
しかし、新興国の人件費が増大したとはいえ、やはりオフショア開発と比べると、ニアショア開発のコスト削減効果は低いです。
オフショア開発ではコストを半分以下にまで抑えることが可能ですが、ニアショア開発のコスト削減率は、最大でも3割程度とされています。
当然ですが、日本国内での開発なので、日本の最低賃金がありますから、どれだけ安くなっても下限が決まっているのです。
このようにニアショア開発は、大幅なコストダウンは期待できない手法なのです。
人材確保が困難
ニアショア開発には、人材確保が困難というデメリットがあります。
地方の企業にも優秀な人材はいますが、そもそも首都圏と比べて人口が少ないため、十分な人材を確保することが難しいです。
十分な人手が集まらない、要求するスキルを満たす人材がいない、指定したプログラミング言語で開発ができるエンジニアがいないなど、人材不足が理由でニアショア開発が頓挫することは珍しくありません。
さらに、ニアショア開発を進めるうえではエンジニアだけでなく、企業間の橋渡しやマネジメントを担う人材も必要となります。
国内の企業同士とはいえ、優秀な人材がこうした役割にいなければ、品質の担保やプロジェクトの円滑な進行は困難です。
一度に多くの人材を確保するオフショア開発と比べて、ニアショア開発はこの点で苦労することになります。
発注先の選定が難しい
ニアショア開発はまた、発注先の選定にも困難があります。
地方は首都圏よりもさらに人手不足が深刻なこともあり、そもそも外注を受けられる企業数が少ないです。
さらに近年のニアショア開発への注目もあり、地方の優良企業は争奪戦になっている現状もあります。
特にベンチャー企業は少数精鋭で活動していることが多いため、スケジュールに余裕がないことがほとんどです。
こうした状況のため、ニアショア開発を実施するのには、外注先が見つからないという問題があるのです。
ニアショア開発を検討するさいは、複数の地方と企業を候補に入れておくことが大切です。
安く高品質の開発を依頼するならAMELAに
今回は、ニアショアについて見てきました。
オフショア開発を得意とする弊社からすると、ニアショアを敢えて導入するメリットは、費用面を考えても小さいと考えられます。
ですが、品質とコストを加味した上でオフショアとニアショアで相見積もりを取っておくことも、重要でしょう。
「高品質なシステム開発を、低単価で依頼したい」
そう考える企業様も多いですが、そんなときは是非AMELAにご相談ください。
弊社は日本法人と現地法人の両方を有するオフショア開発企業です。
ニアショアを検討している企業様の中には
「円安の影響で思ったよりもオフショアのメリットがない」
と聞いて調べている人もいるでしょう。
しかし、日本法人と現地法人の両方を有するオフショア開発企業では、円安の影響は非常に小さく、過去のクライアント様からは非常に好評いただいております。
まずは、開発要件を専任のITコンサルタントにお話しいただき、最適な提案をさせていただければと存じます。