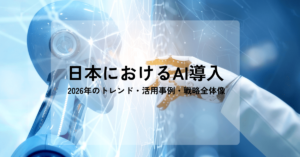不動産テックとは?必要性や技術、具体的な事例を解説

書類作成や内見など、いまだ対面・アナログな業務が多く、IT化が進んでいない不動産業界。
しかし現在、不動産業界は、生産性の低下やデータベースの不備をはじめ、多くの課題を抱えています。
そうした課題を解決して、よりよいサービスを創出するために、「不動産テック」が注目を集めています。
国土交通省が主導する「不動産ID」をはじめ、いま推進が急がれている不動産テック。
VR内見や物件情報サイトなど、すでに大手企業による事例がある進む不動産テックですが、あまり聞きなれない人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、不動産テックがどのようなものなのか、注目される背景や得られるメリット、不動産テックを実現するIT技術、国内の導入事例などを解説します。
不動産テックとは
「不動産テック」とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、不動産テックの意味と注目される背景、不動産テックの必要性、そして日本国内での現状を解説します。
ITを活用して不動産業界の課題を解決
「不動産テック」とは、IT技術を活用して不動産業界の課題を解決したり、新たなサービスを創造したりといった取り組みです。
不動産売買や賃貸、投資といった分野において、企業とクライアント双方のよりよい活動を実現し、これまでにない価値を創出することが、不動産テックの目的です。
すでに実現されている不動産テックの例としては、地域ごとの賃貸物件を検索できるWebサービスや、VR技術を活用した物件内見、インターネット経由の不動産投資などが挙げられます。
これまで不動産業界と関わりのなかったIT企業が数多く参入したことで、不動産テックは大きな進歩を遂げています。
不動産テックの背景
金融業界では、以前からフィンテックと呼ばれるIT技術活用の取り組みが積極的に進められてきましたが、不動産テックが注目されるようになったのは2010年ごろからと、比較的最近です。
アメリカの複数のベンチャー企業が不動産事業へのIT技術活用を始めたことをきっかけに、中国をはじめ世界中に不動産テックが広がりました。
近年は新型コロナウイルス感染症の影響で、対面事業が大きな打撃を受けたこともあり、不動産テックへの注目はさらに増しています。
不動産テックは大きく成長を続けており、国内市場だけでも、2025年には市場規模が現状の2倍まで成長すると予想されています。
不動産テックの必要性と国内の現状
不動産テックがなぜ必要なのか、また日本国内の現状はどうなのでしょうか。
不動産テックが求められる理由としては、業界全体においてIT技術の活用が遅れており、生産性が低下していることが挙げられます。
以前の不動産業界といえば、人海戦術による事業拡大が特徴でした。
しかし、少子高齢化によってこの方法には限界がきたため、新しいやり方が模索されています。
さらに不動産業界には、情報の不透明性や未整理のデータベースなどの課題も抱えています。
これらの問題はIT技術によって解決が可能なのですが、業界内の慣例や日本の不動産への特殊な感覚によって、他の業界よりもITの導入が遅れているのが現状です。
日本において不動産テックビジネスの増加が見られるようになったのは2017年ごろで、まだまだ規模は小さいながらも、少しずつ成長を続けています。
不動産テックでできること
不動産テックに取り組むことで、どのようなことが実現されるのでしょうか。
ここでは、日本の不動産業界が抱える課題である、データベース運用と生産性の観点から解説します。
データの一元管理と運用
国内の不動産業界が抱える大きな問題として、これまで蓄積した情報が未整理であること、そして、物件に関する情報を業界内でも把握できていないことが挙げられます。
総務相が調査によって国内の物件の約30%が空き家であると判明したため、政府は中古物件の流通を推し進めていますが、その取り組みを阻むのが、所有者やリフォーム歴など、物件に関する情報が不透明だという点です。
例えば、賃貸に関しては大手のアプリなどで多少検索ができるようになってきたものの、それでもまだまだ不満が多いのが実情ではないでしょうか。
1つの物件に対して、本来は複数の業者が取り扱っているはずです。
しかし、大手のアプリなどで見てもアプリを経由して問い合わせる不動産会社は、1件であることが普通です。
Amazonの場合だと、1つの商品を複数の会社が扱っていれば、価格競争が起きるなど、消費者にとっては比較検討ができるというメリットがあります。
これが、不動産業界では当たり前でないのです。
他にも、敷金礼金の「1ヶ月分」という表現に対して
・家賃だけに対して1ヶ月分
・管理費を含めた1ヶ月分
など、明確な法律やルールが無く、各不動産業者次第なのだそうです。
このように、色々な部分でシステム管理されていない弊害があります。
だからこそ、IT技術を活用してこうした情報を整理し、大規模なデータベースを構築・運用することは、今後の不動産業界において必須の事業となります。
必要なデータが一元管理されることで、売り手・買い手双方が透明性のある情報をもとに、より高いレベルでの取引が実現されます。
また、有用なデータベースを構築することで、業務の属人化を防ぐこともできます。
少子高齢化によって人手不足が深刻なものとなった現代において、属人化の回避は避けられません。
このように不動産テックは、不動産業界全体の課題を解消し、持続的な事業を実現するために必須の取り組みであると言えます。
生産性の向上
IT技術の活用はまた、業界における生産性の向上にも繋がります。
契約書をはじめとする書類の作成や人材教育といった煩雑な業務は、業務システムの導入・整備によってコスト削減が可能で、結果として生産性の向上に繋がります。
こうした不動産テックの取り組みはDX化と地続きで、これからの企業にとって不可欠な要素といえます。
不動産テックを実現するIT技術と活用例
不動産テックは、さまざまなIT技術によって実現されます。
ここでは、不動産テックを支える主要なIT技術と活用例を解説します。
AI
データベースに蓄積された膨大な情報を、AIを用いて分析することで、さまざまな成果が得られます。
例えば市場価値の算出では、AIが物件に関する多面的なデータを分析し、データベース上の情報と照らし合わせることで、その物件の予測価格を計算することが可能です。
売り手は業務コストを削減でき、買い手は市場相場を把握できます。
また物件情報を扱うWebサービスでは、ユーザーへのおすすめ情報の表示や、精度の高いマッチングといったサービスの提供も、AI技術によって実現されています。
IoT
「IoT(Internet of Things)」は、工場機械や車、冷蔵庫から時計まで、あらゆるモノとインターネットを接続する技術です。
不動産テックでは、こうしたIoTも大きな力を発揮しています。
代表的な例は「スマートホーム」で、これは物件のあらゆる設備にIoTを搭載することで、生活の利便性を高めるものです。
スマートフォンアプリを使ってお風呂を沸かしたり、ドアの施錠を管理したりといったことが可能です。
ドアロックの遠隔操作はすでに企業や宿泊施設で導入が進んでおり、セキュリティが強化されることによる物件価値の上昇が見られます。
VR・AR
新型コロナウイルス拡大をきっかけに広く注目される「VR内見」は、最新の不動産テックの代表例です。
実際に現地へ足を運ばなくとも、VRゴーグルなどのデバイスを用いて、VR上に再現された物件を見学することができます。
VR内見はまた、買い手が仲介業者とスケジュールを会わせる必要がないため、これまでの機会損失を減らすことにも繋がります。
さらに、AR(拡張現実)を活用することで、生成された物件の間取りに、利用者が擬似的に家具などを配置して、生活感などを具体的にイメージできます。
買い手は理想的な物件を選ぶことができ、売り手は売却後のトラブルを避けることが可能です。
ブロックチェーン
インターネット上にある情報を多数のPCで共有することで、データの信頼性を担保する「ブロックチェーン」。
暗号資産を支える技術であるブロックチェーンですが、不動産テックをはじめ、さまざまな分野でも活用されています。
日本でも、物件情報サービスに登録された情報の管理にブロックチェーンを活用する取り組みがおこなわれており、データベースの管理コスト削減を実現しています。
また、物件の契約情報の保守性を高める目的でもブロックチェーンは用いられています。
「スマートコントラクト」と呼ばれるシステムは、煩雑な手続きを経ることなく、契約情報の記録・更新を自動で処理することができ、データの改竄や情報の行き違いなどを大幅に減らすことが期待されています。
不動産テックの事例
ここからは、不動産テックの事例として、IT技術を活用した不動産サービスの具体例を紹介します。
不動産ID
以前の不動産業界においては、特定の物件を示すための共通コードがありませんでした。
そのため、話の行き違いや情報整理の困難さなどによるトラブルが絶えず、国土交通省主導による「不動産ID」の整備が進められています。
不動産IDでは、国内の物件を18桁のコードで識別するもので、物件の可視化が主な目的です。
この取り組みを実現させるためには、ビッグデータの運用をはじめとするIT技術の活用が不可欠です。
不動産IDが整備されることで、これまでは各所に散らばっていた物件にまつわるデータをすべて紐付けて管理することができるようになります。
スペースシェアリング
空き物件を有効に活用する取り組みである「スペースシェアリング」。
現在、インターネットを活用したスペースシェアリングが注目を集めています。
著名な例としては、民泊サービスである「Airbnb」が挙げられます。
インバウンド需要を見込み、空き家や空きスペースを宿泊地として貸し出すサービスで、大きな注目を集めました。
しかし、このサービスには法的な問題があり、次第に貸しスペースの活用などにシフトしていきました。
今後のスペースシェアリングは、ビッグデータによる不動産管理やブロックチェーンで支えられるデータ管理、スパートフォンアプリで簡単にできる利用手続きといった、不動産テックのあらゆるIT技術の活用が進められています。
新しい業界のシステム化もAMELAに
今回は、不動産テックについて見てきました。
不動産業界には、まだまだシステム化されていないからこその問題も多いです。
そういった業界に新たにサービスを作るというのは、リスクも大きいように感じるかもしれません。
しかし、それ以上に得られる利益やブランディングも大きいのではないでしょうか。
AMELAでは、オフショア開発を主軸に、多数の業界のシステム開発の実績があります。
まだまだビッグデータが無いような業界でも、工夫次第でデータの活用は可能です。
是非、一度ご相談いただければと思います。