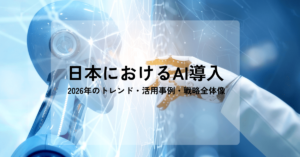テレワークにおける電話取次の課題と解決方法について

コロナウイルスが国内で蔓延して以降、企業ではテレワークが急速に普及していきました。
感染症対策の一環で始まったこのテレワークですが、副次的に多くのメリットがありました。
例えば、
・出社をしなくて済むことによる時間の効率的な活用
・育児や介護を理由に働くことができなかった人材の登用
・勤務地に拘る必要がなくなったことによる優秀な人材の発掘
など、テレワークには多くの産物がありました。
その一方で、テレワークによる課題も多くあります。
例えば、
・上長の目が行き届かないことにより業務が疎かになっていないか
・部下とのコミュニケーションが取りにくい
・取引先からの電話対応が難しい
などといったことが挙げられます。
今回の記事ではこれらの課題の中でも、特に解決の重要度合いが高い『電話対応』について取り上げ、その解決方法についてご紹介をしたいと思います。
テレワーク時の電話対応における課題
まず始めに、これまでテレワークの普及を推し進めてきた中で、電話対応に関してどのような課題が浮き彫りになったのかを解説します。
担当者の不在
1つ目の課題は、会社に取引先などからの入電があった場合に、担当者が出社しておらず応対ができないというケースです。
これは、
「緊急時の場合などにフットワークが重くなってしまう」
という大きなデメリットがあります。
また、緊急時でなくとも取引先からの連絡に即座に応えられないというのは、取引先にとっては対応に不満を感じてしまうかもしれません。
社用携帯が行き届いていない
2つ目の課題は、会社貸与の携帯やスマートフォンがテレワークをおこなう全社員に普及していないというケースです。
テレワーク時の基本的な連絡手段はメールやチャットが主で、その他にはZOOMなどによるオンライン会議などが挙げられます。
しかし、急ぎで連絡を取りたい場合や、メールなどで文字起こしをするのが負担に感じる時には、電話を使って済ませたい場合もあります。
携帯が支給されていないことで電話でのやり取りができない、もしくは個人携帯を使って連絡をするといった事態が生じてしまいます。
これは、後述する通話料の問題以外にも、
「プライベートの携帯に顧客や取引先の電話番号が入っている」
という状態になります。
PCほどではないものの、スマホもウィルスによるハッキングは問題視されており、情報漏洩に繋がる危険性があります。
個人電話による通話料の負担
上述した個人携帯を使っての連絡をおこなった場合、その通話料金は誰が負担するのでしょうか。
これが3つ目の課題です。
通話し放題のプランに加入している場合はいいかもしれませんが、当然そうではないケースもあります。
これまでの一般的な電話対応
以上がテレワークの普及に伴う、電話対応における課題です。
ではこれらの課題を抱えながら、企業はこれまでにどのような対応をおこなってきたのでしょうか。
担当者からの折り返しやメール
担当者が不在の場合は、担当者本人から折り返し連絡するという対応です。
これについては先にも述べたように、緊急時の対応が課題です。
しかし、課題という認識は持ちつつも、具体的な対策を取らぬままやむを得ずこの対応を継続しているケースもあります。
留守電設定
会社の電話対応自体をとりやめ、留守電設定にするという場合もあります。
この場合の取引先への対応は2つあります。
1つは担当者本人、もしくは別の誰かが出社した際に留守電を確認して対応するケースです。
もう1つは、会社代表番号での電話対応はせず、直接担当者と連絡を取ってもらうよう取引先へ依頼するというケースです。
電話当番の交代制による出社
電話当番を交代制にして出社するという対応をとる企業もあります。
たまたま担当者が出社している場合には即時対応可能ですが、そうでない場合は担当者への取次や折り返しなどといった対応を取らざるを得ません。
電話取次で起こりうるリスク
テレワーク時の電話対応や取次方法について解説をしました。
その場しのぎの対応ばかりであり、具体的な対策は実施されていないケースの多いことがおわかりいただけたと思います。
では、ここで述べたような対応を今後も続けた場合にどのようなリスクが待ち受けているのでしょうか。
顧客満足度の低下
1つ目のリスクは顧客満足度の低下です。
取引先が問い合わせなどの連絡をしてくる場合は、当然解決したい課題を抱えていると考えられます。
その場合に折り返しなどでタイムラグが生じてしまうと、取引先にとっては不満が募ります。
今後も同様の対応を継続することで、最悪の場合は満足度だけでなく、
「顧客に対して不誠実な対応をする会社」
というレッテルを貼られてしまうなど、会社としての信頼自体を失いかねません。
営業機会の損失
2つ目のリスクは営業機会の損失です。
スピードを求める取引内容の場合、電話の取次などで時間を要してしまっては、ビジネスチャンスを逃しかねません。
より早く細やかなサービスを提供する企業に取引先を奪われてしまう可能性があります。
また、既存ビジネスだけでなく、新規ビジネスや新規顧客の開拓などについても同様で、対応の遅さによりその機会を失ってしまうかもしれません。
取次担当者の業務負担
3つ目のリスクは取次担当者の業務負担が大きいという点です。
電話の取次ばかりに時間を割かれてしまうことで、その担当者の本来業務が疎かになってしまい、生産性の低下に繋がるという懸念があります。
これまでは
「直接会う予定があったから、その時にまとめて聞こう」
と思っていた内容も、テレワークによって電話で質問してくる可能性があります。
そうなると、これまで以上に電話の件数が増える可能性があるでしょう。
そんな中で、コールの度に都度手を止められてしまっては、作業効率が非常に悪くなります。
早く問題を解消しないと担当者の不満は募るばかりで、最悪の場合は離職による人材流出という事態も起こり得ます。
テレワーク時の電話取次問題を解決するには?
上述したようなリスクを避けるためにも、企業はテレワーク時の電話対応について、具体的な対策や仕組みを検討しなければなりません。
ではどのような対策を講じることができるのか、これらの課題を解決することができるサービスについて紹介をします。
電話代行サービスの利用
最初に紹介するのが電話代行サービスの利用です。
社外の代行サービスに電話を転送し、代理で対応をしてもらうという方法です。
電話取次をする必要がないため、生産性の低下を防ぐことができます。
一方で課題としては、代行サービスをしてくれる業者への教育やマニュアルの作成など、運用を開始するまでの準備に時間とコストを要することが挙げられます。
また、営業の特徴として「あとひと押し」というような場面がありますが、代行サービスに同等のクオリティを求めるのは難しいです。
そのため営業機会の損失という意味では、全ての課題解決には至らず、その点に関しては別途検討が必要でしょう。
アプリの利用
次に紹介するのがアプリの利用です。
固定電話の番号を使い、スマートフォンから発着信ができるようになるというアプリがあります。
このアプリをインストールするだけで利用可能です。
スマートフォンから電話をかけると、相手には固定電話の番号が通知され、また、着信も可能であるため、取次や転送なども不要といった利便性があります。
誰でもすぐに利用でき、導入に要するコストなども低いことから、取り扱いやすいサービスの1つであるといえます。
転送サービスの利用
次に紹介するのが転送サービスの利用です。
転送サービスとは、会社にかかってきた電話を担当者の携帯やスマートフォンなどに自動で転送するというサービスです。
このサービスを利用すれば、先に述べたアプリと同様に、テレワーク時でも電話を受けることが可能になるため、担当者からの折り返しや、電話当番の交代制による出社などを回避することができます。
転送サービスの使い方は、事前に電話番号を登録しておくことで、どこにいても電話が自動で転送されるというものです。
転送サービスを利用することで、取次の負担軽減になるだけでなく、取引先への対応もスムーズにおこなうことができます。
クラウド電話の利用
最後はクラウド電話の利用です。
クラウド電話とは、インターネット環境を用意することで、内線や外線、転送などを自由におこなうことができるサービスです。
これまでにオフィスなどではPBXといわれる電話交換機が設置されていました。
PBXとは、電話回線を組み合わせて接続することで、内線同士の接続や、内線と外線の接続を制御し、社内外の電話網を構成するといった役割を担っているハードウェアのことをいいます。
このPBXをクラウド上に設置して利用するサービスのことをクラウド電話といいます。
PBXをクラウド化することで様々なメリットがあります。
これまでPBXをオフィスに設置する際は、ハード機自体を購入する必要がありました。
会社拠点が多い場合はその分PBXを設置する必要があったため、相当なコストを要していたという背景があります。
更にはPBX導入に要するコストに加え、保守費用なども発生していました。
また、これ以外にもPBXを設置する場所の確保など、様々な課題を抱えていました。
PBXをクラウド化をすることで、コスト面や場所の確保などの問題をまとめて解消できると考えられています。
一方でクラウド電話にはデメリットもあります。
クラウド電話を利用するにあたっては、インターネット環境が整備されていることが前提となります。
そのため、通信環境が不安定の場合は音声が途切れたり、電話が繋がらないといった事象が発生しやすくなります。
クラウド電話の導入コスト自体は低くとも、ストレスフリーに利用を継続するためには、インターネット環境を整備するための初期費用やランニングコストを踏まえた上での導入検討が必要になります。
以上のサービスを活用することで、テレワークの更なる浸透と、電話取次問題の解消が期待されています。
社内環境をITで整備。AMELAに相談を
今回は、テレワークによって難しくなった「電話取次ぎ」について見てきました。
環境が変わる中で、ITを活用して適切な対応を取れば、これまで以上にチャンスが有ることも多いです。
例えば、営業マンがテレワークによって客先へ行く機会が減った一方で、
「テレビ会議でのアポイント頻度は増えた」
とう話があります。
互いに準備や移動時間が必要ないため、気軽に連絡を取り合えるために、チャンスが増えた企業もあるのです。
このように、変化はあるものの、やり方を間違えなければチャンスも大きい時代です。
ITの活用は必須であり、是非AMELAにご相談いただければと存じます。