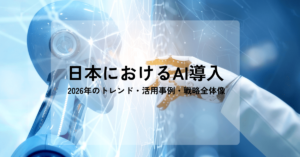システム開発を成功に導くプロジェクト体制図とは?具体例と作成におけるポイントを解説
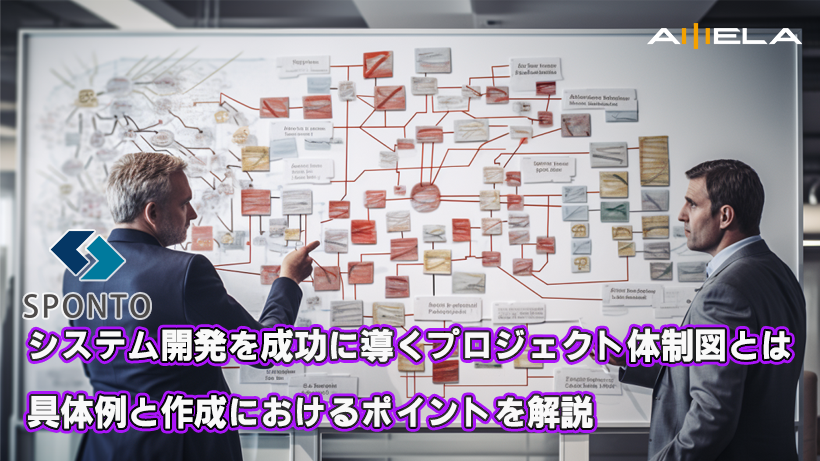
社内で取り扱う情報はその企業全体の財産であることから、情報は一元的に管理されていることが理想的です。
そのため、システム開発をおこなう際には部門を横断したプロジェクト体制を築き、全社一丸で取り組むのが一般的です。
しかし、業務上関わることない部署とコミュニケーションを図るのは、想像以上に難しいものです。
プロジェクトが想定通りに進まず、結果的に期待していたシステム開発ができないというケースは往々にしてあります。
システム開発を成功に導くためには、最適なプロジェクト体制を築かなければならず、プロジェクト体制次第で結果が全て決まると言っても過言ではありません。
この記事ではシステム開発を成功に導くためのプロジェクト体制とはどのようなものか、具体的な内容と作成のポイントを紹介します。
プロジェクト体制図とは
そもそもプロジェクト体制図とはどのようなものかを解説します。
プロジェクト体制図とは、特定のプロジェクトや組織のプロジェクトマネジメント体制を視覚的に表現したものを指します。
例えば、システム開発のプロジェクトを立ち上げるにあたり、プロジェクトオーナー(依頼元)は誰なのか、プロジェクトの責任者と実行役のリーダー、各役割ごとの構成メンバーなどを明示することで、誰が何の役割を担うのかをわかるように構成されているのが一般的です。
他にも、UIの担当やバックエンドの担当など、1つのシステムを作るにも分野が分かれており、それぞれ専門のエンジニアが担当する事も多いです。
プロジェクトの規模が小さければ兼任も多くなり、規模が大きくなれば体制が複雑になります。
いずれにしても、プロジェクト体制図があることで、チーム全体を把握することが出来ます。
プロジェクト体制図の必要性
プロジェクトを立ち上げる際に体制図の作成は必須です。
なぜプロジェクト体制図が必要なのか、その理由を解説します。
プロジェクト体制図を作成することは、以下に記すように様々なメリットがあります。
プロジェクト全体の可視化
プロジェクト体制図を作成することでプロジェクト全体を把握することができます。
プロジェクトのステークホルダーや責任者の把握など、そのプロジェクトを構成する人員や業務を網羅的に確認できるようになります。
プロジェクトの目的とやるべき事を見失うことのないよう、マクロな視点で判断をするために体制図は効果を発揮します。
役割と責任の明確化
プロジェクト体制図は組織の透明性向上、および役割と責任を明確化するために必要です。
プロジェクト体制図は、プロジェクトに関与するメンバーやステークホルダーが誰であるかはもちろん、それぞれの関係者がどのような役割と責任を担当しているかを明確に示すことができます。
これにより、組織全体を通じプロジェクトの進捗に対して、誰がどのように関与しているかが理解しやすくなります。
役割と責任を明確にすることで、プロジェクトを成功に導くために成すべき事を取りこぼさず、メンバー一人一人が自分事として業務に携わる空気と風土の醸成につながります。
また、明確な役割を決めることにより
「デザイン部分について確認するならAさん」
のように、質問する人や担当者が明確になります。
特に大きなプロジェクトでは、参画人数も多くなるため、指揮系統がはっきりと分かる必要性があるのです。
円滑なコミュニケーションの促進
プロジェクト体制図は、チームメンバーやステークホルダー間のコミュニケーションを促進するために必要です。
プロジェクトを構成する業務について、誰が何の情報を持っているのか、誰に何を報告するべきなのかが体制図により可視化されます。
これにより、認識の齟齬や情報不足を防ぐことができ、円滑なコミュニケーションの促進につながります。
適切なリソース配分
プロジェクト体制図は、組織内のリソースを適切に配分するために必要です。
プロジェクトを進めるにあたっては、人員の配置、技術の共有、予算の捻出など、企業にとって多くのリソースを割かなければなりません。
しかし、プロジェクトの全体像がわからなければ、どこにどれだけのリソースを割くべきなのかが曖昧になってしまいます。
プロジェクト体制図を用いて各部署やメンバーが担当する範囲を明確にすることで、業務の重複を避けるだけでなく、余計なコストをかけずに済むなど、効率的な作業が可能になります。
課題の早期発見
プロジェクト体制図は課題の早期発見にも役立ちます。
プロジェクト体制図により、特定の担当者や部門がプロジェクトの側面に責任を持つことが明確になることから、プロジェクトの進捗に問題や遅れが発生した場合、それがどの部分に関連しているのかを迅速に特定できるようになります。
これにより、課題やトラブルに対しスムーズに対処することが可能です。
例えば、最終的にシステム全体のテストを行う結合テストでは、フロントエンドもバックエンドも開発が完了している必要があります。
また、本番用のサーバーなどのインフラも用意できている事が必要ですし、テスト項目の洗い出しも終わっている必要があります。
これらがそれぞれチームとして分かれている様な場合、どこかのチームの遅れが結合テストそのものの遅延に繋がります。
そのため、遅れが出そうな場合には、リソースを再配置した上で速度を上げる必要があるのです。
総じてプロジェクト体制図は、プロジェクト全体の透明性、コミュニケーションの円滑化、リソースの最適な利用など、プロジェクトの成功に向けてとても重要な役割を果たします。
プロジェクト体制図作成におけるポイント
プロジェクト体制図を作成する際は、そのプロジェクト全体が把握できるよう、関連する情報は抜け漏れなく作成しなければなりません。
プロジェクト体制図を作成する際はどのような情報を盛り込む必要があるのか、作成におけるポイントや注意事項を解説します。
役割と責任の範囲が定まっているか
プロジェクト体制図を見ることで、関係者の役割、および責任の範囲が明確になっていなければなりません。
例えば、システム開発のプロジェクトにはIT部門はもちろん、実際にそのシステムを業務に用いるユーザー部門も参加するのが一般的です。
そのプロジェクトにおいて、ユーザー部門に期待する業務は何なのか、ユーザー部門の責任者は誰で、その責任者の果たすべき仕事は何なのかといったように、部門単位、人単位で役割と責任の範囲を体制図で定めることが重要です。
組織体制が考慮されているか
プロジェクトを推進する上で、組織体制が考慮されているかを見極める必要があります。
プロジェクトを成功に導くためには優秀な人材を抜擢しなければなりません。
しかし、優秀な人材は往々にして忙しくしているものです。
普段の業務で多忙を極めている中、新たなプロジェクトメンバーに抜擢することで、組織の業務が回らなくなる恐れがあるだけでなく、個人にとっても心身の不調を来しかねない危険性があります。
プロジェクトメンバーの人選は組織の事情を考慮し、その上でプロジェクト体制図の作成が求められます。
ステークホルダーが適切に組み込まれているか
プロジェクト体制図作成においてステークホルダーを見落とさないよう注意が必要です。
実行部隊はプロジェクト推進の上で必須のため見落とす可能性は低いですが、誰が何の決裁権限を持っているのかということについて、単純に見極めるのは難しいものです。
実は関係ないと思っていた人が特定の業務に決裁権限を持っていた、ということも考えられるため、後になって「俺は聞いていない」などといったトラブルにならぬよう気を付ける必要があります。
プロジェクト体制図の具体例
プロジェクト体制図を作成する際のポイントを踏まえた上で、作成の具体例を解説します。
プロジェクト体制図には以下に記す内容を盛り込むといいです。
全体を統括する責任者の設定
真っ先に盛り込むべきはプロジェクト全体を統括する責任者(プロジェクトマネージャー)の記載です。
プロジェクトマネージャーはプロジェクト全体を統括し、計画、実行、監視、制御などのプロジェクトマネジメントの責任を担当する個人を指します。
プロジェクトマネージャーは通常、最終的な意思決定権を持つことが期待されており、体制図の最上位に位置します。
プロジェクトにもよりますが、一般的には顧客折衝や人員の調達までを行う必要があります。
また、責任者とは少し異なりますが、ステークホルダーの記載も必要です。
ステークホルダーはプロジェクトに関与する利害関係者や関連者を指し、彼らの期待や要件を考慮して開発をしなければなりません。
プロジェクト体制図で表すと組織階層の中には入りませんが、意思決定権は強いという位置付けです。
役割に応じたチームの設定とリーダーの任命
プロジェクトはタスクごとに業務を分解し、その業務に対して最適な組織とメンバーを割り当てます。
プロジェクト体制図には、そのプロジェクトに所属する組織全体の体制や階層構造に加え、各組織ごとの責任者を明示する必要があります。
チームに求められる役割を果たせる専門メンバーの任命
組織階層と責任者を任命した後は、プロジェクトメンバーを決定します。
彼らはそのプロジェクトにおいての実務担当者として、それぞれに異なる専門分野や役割を担当し、プロジェクトの成功に寄与する人たちです。
プロジェクト体制図では組織ごとのリーダーの一つ下の階層に位置付けられます。
コミュニケーションフロー図と組織階層の見える化
関係者の洗い出しができた後は、コミュニケーションの経路を可視化します。
コミュニケーション経路とは、 チームメンバーやステークホルダー間のコミュニケーションの経路やフローのことを指し、報連相をおこなう際などに、
『誰に対して、何を報告する必要があるのか』
ということを視覚的に表現したものです。
これにより、意思決定権者の把握や、関係者のパワーバランスが一目瞭然となるため、効果的かつスムーズなコミュニケーションを図ることが可能になります。
また、併せて役割と責任を記しておくことで、関係者自身もそのプロジェクトで何を期待されているのかを理解しやすくなります。
プロジェクトはフェーズごとに果たすべきタスクが異なる場合があります。
そのような場合は、フェーズごとの主要な担当者を示したり、スケジュール感を可視化するなどといった対応も必要です。
以上のように、プロジェクト体制図はプロジェクトチーム全体にとっての共通理解を促進し、コミュニケーションの向上やプロジェクトの透明性向上に寄与するものです。
プロジェクト体制図はプロジェクトの成功に不可欠な要素になります。
安全なプロジェクト運営はAMELAに
今回は、プロジェクト体制図について見てきました。
今回の内容は、規模が大きな案件や、しっかりとした準備が必要なプロジェクトでは利用される事が多いですが、反対に予算に余裕が無いようなプロジェクトの場合には、こういった図を作る事は無いでしょう。
しかし、プロジェクトを安全に行う上で必要なケースが多く、プロジェクトの成否を分けることもあるでしょう。
AMELAでは、通常のシステム開発と比べて
・エンジニアの単価が安い
・余裕のあるスケジュール感でも相場より安い
という開発が可能です。
オフショア開発により、海外の優秀なエンジニアを安価で参画させることが出来るため、各プロジェクトの品質も非常に高いです。
「ただ作るだけ」
ではなく、しっかりとした品質のものを、予算内に作る。
そのためにも、是非一度システム開発の際にはご相談頂ければと思います。