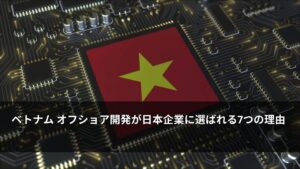フレックスタイム制を効果的に導入するポイント
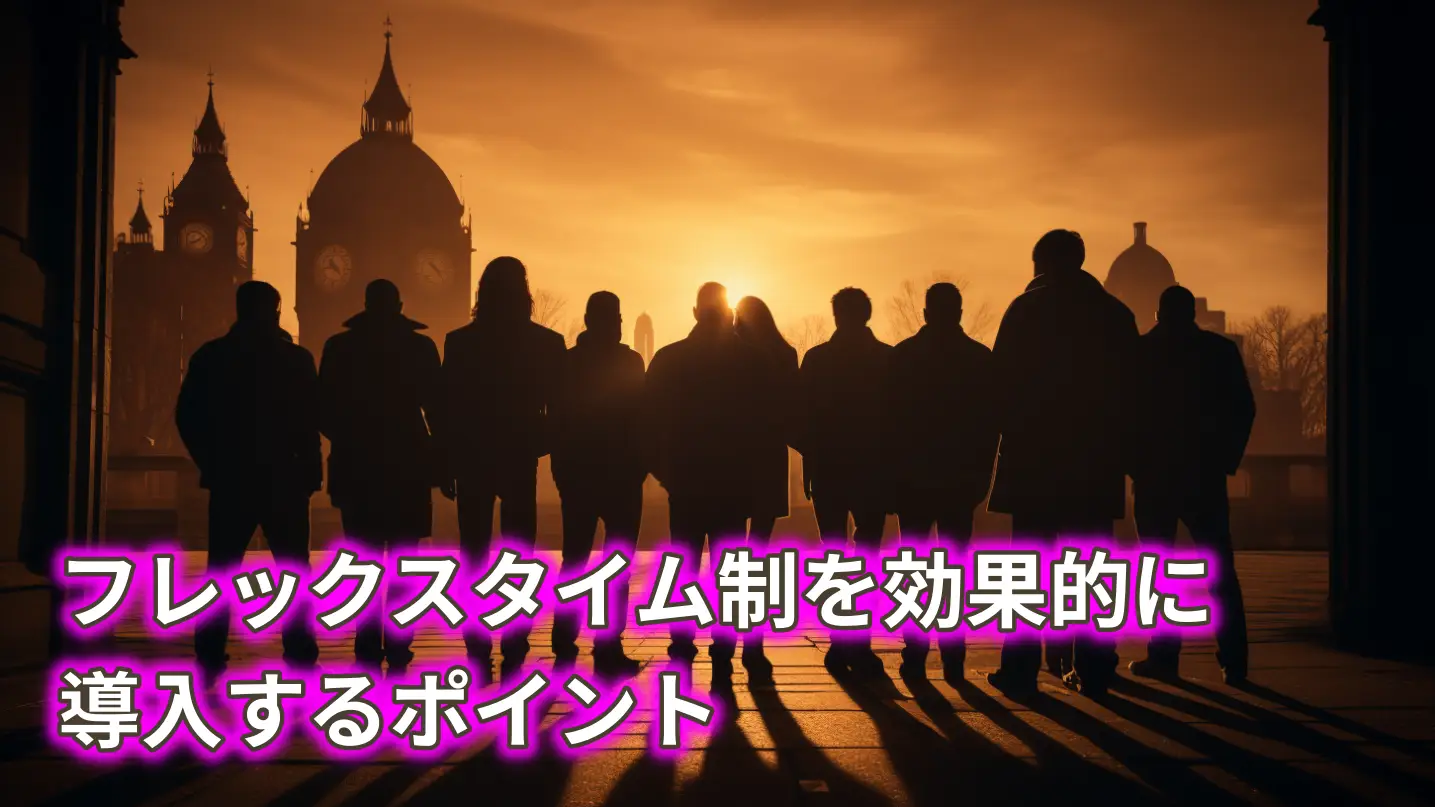
多くの企業で導入が進んでいるフレックスタイム制ですが、効果的に運用できている企業は少ないと思います。中には「フレックス制は本当に役立つのか」「どうすればいいのか効果的に運用できるのか」など、悩みを抱えている企業もいるでしょう。 そこで今回は、フレックスタイム制の概要からメリット・デメリット、課題の改善方法などをご紹介していきます。これから導入を検討されている企業や、課題を抱えている企業はぜひ参考にしてください。
そもそもフレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、コアタイム+残業時間の精算を行うことで、業務時間を柔軟に設定する方法です。英語の「柔軟(Flex)」から由来した言語で、従業員自身で労働時間を管理できる特徴があります。 コアタイムを設定する企業が多いですが、法令上必須ではありませんので、コアタイムが設定されていなくても問題はありません。 基本的には、1か月単位と3か月単位で残業時間の精算が行われます。
フレックスタイム制の導入にともなう手続き
フレックスタイム制を導入する時は、以下の事項を定める労使協定を締結する必要があります。また、3か月単位で精算を行うフレックスタイム制では、労働基準監督署に届出を提出する義務があるので注意です。労使協定で締結する事項1.対象になる労働者の範囲(部署や個人単位でも可能)2.清算期間(1か月or3か月)3.清算期間における総労働時間=法定労働時間4.目安となる1日の労働時間 これらの項目は必ず契約書に記述し、従業員と契約を結ぶ必要があります。 また、任意で以下の2つの事項を設定します。 1.フレックスタイム2.コアタイム 任意であるため、記述されていなくても法令上問題はありません。
フレックスタイム制を導入するメリット
フレックスタイム制を導入するメリットは以下の3つです。それぞれ解説します。
1.労働時間が固定されない
フレックスタイム制では、従業員自身が労働時間と残業時間を管理することで、ライフワークバランスをコントロールできます。 そのため、子育て中や介護・資格試験の勉強など、時間が必要な社員でもストレスなく働くことが可能です。 従業員の満足度を高めることにつながり、結果、業務に対するモチベーションの向上や離職率の低下など、さまざまな面で効果を発揮するでしょう。
2.残業コストの削減につなげることが可能
フレックスタイム制では、1か月もしくは3か月単位で労働時間の通算ができるので、日ごとに発生する残業時間を計算する工程を省くことが可能です。 また、社員の集中しやすい時間に労働してもらうことで、生産性が向上し、結果、残業時間が少なくなるケースもあります。
3.採用時のアピールになる
フレックスタイム制は、採用時のアピールポイントとして効果が高いです。 一般的な業務形態と異なり、状況によっては「朝早く通勤する必要がない」「夜遅くまで残業せず早めに退社できる」ため、ホワイトな職場の印象を持たれるでしょう。 人材市場が縮小し、採用活動が難航している現在、フレックスタイム制を導入している企業は、採用活動において一歩有利になります。
フレックスタイム制を導入するデメリット

さまざまなメリットがあるフレックスタイム制ですが、一方でデメリットも存在します。それぞれ解説するので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
1.評価軸の不透明化
フレックスタイム制では、出社時間や退勤時間が個人の裁量によって決まるので、労働時間による評価軸は複雑になります。 総合的に長い時間働いた人が評価されてしまうと、フレックスタイム制を実施する従業員が減り、仕組み自体形骸化してしまうでしょう。 成果物の質や量、従業員同士のコミュニケーションやスケジュール管理など、具体的な指標を設定し、従業員のモチベーションが維持できる評価制度を整えることが大切です。
2.システムの運用が複雑
フレックスタイム制の運用は労働時間の計算など、手間がかかりやすいデメリットがあります。 1か月単位でも3か月単位でも、所定の月の労働時間は決まっています。上限を超えないように残業時間を管理する必要があり、面倒です。 これらの管理は人の手で行うと、ヒューマンエラーが起こる可能性があるのでITツールの導入をおすすめします。 今は従業員個人で勤怠時間を入力し、データを集計して月の労働時間を自動で算出してくれるツールが提供されており、作業の短縮化を図ることができるでしょう。
フレックスタイム制を実施することで生産性向上を目指す
この記事では、フレックスタイム制について解説しました。 従業員の意思で柔軟に労働時間を管理できるフレックスタイム制は、業務効率化やモチベーションの向上など、さまざまな面でメリットがあります。 一方で、時間管理が苦手な従業員に対してのフォローや評価軸の再検討など、運用時にかかる負担も多いデメリットがあります。 採用する企業も増えてきましたが、まずは自社に似た事例を確認し、導入が上手くいくか検討してみましょう。採用して得られた効果が自社でも期待できそうなら導入し、改善を重ねて最適な運用を目指すことが大切です。